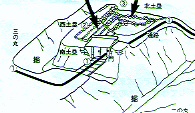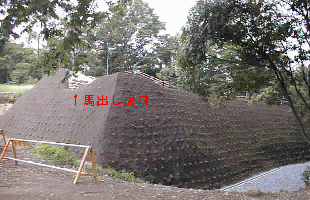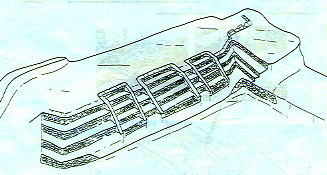| (鉢形城歴史館オープン) 平成16年10月16日 | |
 |
展示内容は、鉢形城の模型と映像で、歴史と遺構を詳しく解説してくれます。その他の事は、パネルと映像で説明してくれます。発掘品に関しては、2ケース展示されてますが、八王子城などと違い、開城でしたのでやはり少なかったみたいです。鉄砲の玉は只今4個発掘された様ですが、外曲輪の水田化した水堀を発掘すれば、多くの玉が発掘されると思います。現段階も発掘調査が進行中ですので、今後も楽しみに待ちましょう。 今回年二回行われる特別展が行われていて、秩父郡吉田町椋神社に奉納されている、氏邦所用の「筋兜」や、鎌倉時代の武蔵七党の中心的勢力だった秩父氏の子孫で、鉢形城の秩父曲輪に屋敷があった秩父孫次郎重国所用の「五枚胴具足」が展示されていて(いずれも本物)、直に見れた事が大変嬉かったです。 |
| (本丸) |
  (左:本丸 後方は荒川の断崖、右:石垣) |
| 本丸の部分は、3つの郭に分かれていて、北条氏邦が入る前の鉢形城は、本丸の部分だけだったろうと言われています。3つの郭はそれぞれ堀切により区切られ、荒川側には土塁があります。 |
  (左:本丸と御殿下曲輪間の土塁、右:本丸の井戸址) |
 (本丸から、秩父方面を見る〉 |
|
|