| 『石間城』 |
 (城の水源跡) |
 |
|
|
|
各地に将門伝説は残っていますが、ここ吉田町の城峰山の山頂付近にも残っています。それが、石間城です。下野 の藤原秀郷に追われた平将門が、ここ石間城に立てこもって戦ったが遂に落城、将門は城の裏にある岩穴に隠れて いた所を捕らえられたと言います。しかしその後、あちらこちらで将門そっくりの影武者が七人捕らえられました 。そこで秀郷は、将門の侍女である桔梗姫を捕らえて、『八人の首をはねる事もあるまい。』と問い詰めた所桔梗 姫が、『食事をする時、こめかみが一番良く動くのが、上様でございます。』と秀郷に教えたと言う。とうとう本 物の将門が見つかり、首をはねられる時に将門は、『桔梗あれども花咲くな。』と言い残したと言います。その事 からか、城峰山では桔梗の花が咲かないそうです。桔梗姫は後を追って亡くなったと言うのに。なお、お屋敷場と 言う所からは以前、刀片、鏡、釜などが見つかったと言います。頂上の展望台からは、関東平野が一望でき、近く には城峰神社があります。
|
| 『龍ケ谷城』別名吉田の盾 |
  (左:龍ヶ谷城遠望、右:二の丸と三の丸間の折の付いた土塁) (左:西方最前線の掘り切り、右:本丸の虎口) |
 (龍ヶ谷城の西方に有る、物見平) |
 |
|
|
|
別名「吉田の盾」と言われた龍ケ谷城。こちらも鉢形城の有力支城の一つで、城主は久長但馬守。こちらも武田氏の進入に対して作られた城です。永録12年の武田軍との戦いは、ここでも行われた。 (石間谷の戦い)この戦による感状が3点残っていると言います。城の遺構は、山頂部に良く残っていますので、武田軍との戦の事を思いながら訪れては如何でしょうか。尚、天正18年の豊臣秀吉による小田原北条氏の攻撃の時、城主久長但馬守と山岸主膳之言います。後に鉢形城落城後、久長但馬守は上杉景勝の家臣になったそうです。鉢形落城哀史より。(著者 故四方田美男氏)
|
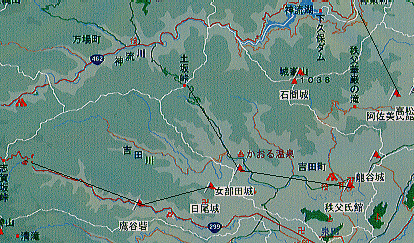 (武田軍侵入に備えての、各城郭) |
| 永録12年の武田軍の侵入の時は、武田軍本隊は直接鉢形城へ。別動隊は、秩父郡内の鉢形城の各支城攻撃を行った。武田軍の別動隊は、吉田町の土坂峠を越えて来た。そこを、土坂峠の 監視を行っていた女部田城で発見し、秩父郡内の各支城及び、鉢形城へ連絡した。志賀坂峠の監視は、鷹谷砦、土坂峠の監視は、女部田城、出牛峠の監視は、高松城がした。その後、日尾 城では三山谷の戦い、龍ヶ谷城では石間谷の戦い、千馬山城では三沢谷の戦いが繰り広げられたが、各城とも善戦し落城はまのがれました。(武田軍の戦法に、無理強いしないと言う事も ありましたが。)その後武田軍の別動隊は、本隊と合流し鉢形城を包囲したが、落とせなかったと言う事です。 |